いつも「管理栄養士の食事ノート」をお読みくださり、どうもありがとうございます。
先週はとても寒かったですね。
寒いときには温かい飲み物が飲みたくなります。
私は葛湯が好きでよく飲んでいます。
味も自分好みで、お気に入りの材料だけを使った葛湯を作っています。
葛粉大さじ1/2、てんさい糖小さじ2、金時しょうが粉を少々、水100mlを
すべて混ぜ、小さいお鍋に入れて弱火にかけます。
透明になりとろみが出たら出来上がり。
私が子どもの頃、母がよく片栗粉に砂糖を入れてお湯で溶かしとろみをつけたものを作っていました。
本葛粉は値段が高いから、同じでんぷんだから片栗粉でも良いのでは?と以前は思ったこともありました。
専門ではないので詳しくはありませんが、
馬鈴薯でんぷんはマクロビオティックでは陰性で身体を冷やすと言われています(葛粉は陽性より中庸)。
どうせなら、身体を温めてくれるほうを摂りたいと思いました。
金時ショウガも身体を温めてくれ、ほんのり良い香りがし、葛湯が美味しくなります。
市販のお湯に溶かすだけで出来る葛湯のもとの中には、お砂糖がたくさん入っていたり、葛粉だけではなく、馬鈴薯でんぷんが含まれていたりするものもありますので、材料にこだわりたいかたはぜひ、手作りをオススメします。
本葛粉は値段が高いですが、一回に使う量は少しずつですので、意外とお安くなります。
葛も馬鈴薯も同じでんぷんで栄養素やエネルギーだけでみると仲間なんですが、植物が違えば持っている力は変わります。
栄養指導では時おり、食べ物をグループ分けして、グループ内は交換可能という方法をとります。
例えば緑黄色野菜で、ほうれん草が食べられなくても人参を食べれば似たビタミンが摂れるとか、
ごはん〇〇gとパン〇〇gはエネルギーが一緒とか。
これは栄養素やエネルギーのみを焦点として考えたい場合は有効な手段ですが、
食べ物となってくれている命にはみんな違った個性があることを忘れて置き換えばかりしてしまうと、逆にバランスを崩した食事となってしまうので注意が必要です。
人間と一緒で、たとえ似ているところがあってもみんな違った個性がある、ということを忘れないようにしたいと思っています。
ちなみに本葛粉は整腸作用があり、お肉の食べ過ぎなどで子どもが下痢をした時には、すりおろしたりんごを葛とじにしてお手当として使うそうです。
葛粉は色々な使い道がありますので、常備しておいてもよさそうですね。
JR和歌山駅東口より徒歩1分。漢方相談・ホメオパシーを中心に、かかりつけ薬局として、自律神経失調・皮膚疾患・妊活・がんに伴う諸症状などの、ご相談をお受けしております。
和歌山県和歌山市太田1丁目13-8 エヌ・アイ・シービル1F
(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00
[木] 9:00~13:00
[土] 9:00~17:00
定休日 日・祝日
お問い合わせフォームはこちら
(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00
[木] 9:00~13:00
[土] 9:00~17:00
定休日 日・祝日
お問い合わせフォームはこちら




- トップページ
- >
- こうしん堂ブログ

チェック |
症状・疾患 |
会社概要 |
こうしん堂に隣接コインパーキングがございますのでご利用下さい。
ご購入いただきましたお客様には、ご滞在時間に応じた対応をさせて頂いております。
満車の際はお声かけ下さい。
|
頂けます  店頭でご確認ください。 店頭でご確認ください。 |

よい寄せられるご相談
■女性のお悩み■妊活「不妊・子宝」
■お肌トラブル・美容
■自己免疫疾患・橋本病・バセドウ
■癌「がん」
■消化器疾患
■痛みのご相談
■自律神経失調・メンタル
■呼吸器・耳鼻科・眼科疾患
■尿のトラブル
■生活習慣病
■その他

漢方相談・ホメオパシーセッション
通常、店内のご相談スペース【他のお客様と仕切られた場所】にて行っております。奥には、さらに個室相談スペースを設けております。ご希望の際は、お申し出下さい。
秋の夜長は・・・

葛湯で温まる
カテゴリ : [月]管理栄養士の食事ノート
2017-12-18 08:00:00
石狩鍋風みそ汁
カテゴリ : [月]管理栄養士の食事ノート
いつも「管理栄養士の食事ノート」をお読みくださり、どうもありがとうございます。
とても寒い日が出てきましたが、そんな時は温かい汁物を食べるとホッとします。
テレビで「秘密のケンミンショー」をたまに見るのですが、以前「石狩鍋」について特集していて、とても美味しそうでした。
そこで真似っこしてお味噌汁を作りました。

材料は、人参、キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、えのきだけ、鮭のアラ、味噌、酒粕、だし汁、です。
材料を食べやすい大きさに切り、だし汁でやわらかくなるまで煮込みます。
最後に味噌を溶き入れ酒粕を加えて出来上がりです。
とても簡単にアレンジして作りました。
本場のかたにはダメ出しされそうですが、「石狩鍋風」ということでお許しくださいね。
お味噌汁はレシピ通りきっちりと分量を守らなくても失敗しにくく、美味しく出来上がるので嬉しいです。
酒粕が無いときは味噌だけでも野菜の甘みが出て美味しくいただけます。
テレビ番組では、本場の石狩市では鍋と言うより大きなお椀によそってお味噌汁のように食べると言っていました。
そして、鮭は身ではなく必ずアラを入れるそうです。
身は焼いて食べるとか・・・。
番組ではおうちのお母さんが大きな鮭をまるまる一匹さばいていました!すごいです!
魚のお味噌汁は好きなのですがレパートリーが少なかったので、うれしい発見でした。
こちらのブログで以前書かせてもらいました「一汁一菜」を楽しんで実行しています。
子どもも好き嫌いは色々あるのですが、お味噌汁は必ず完食してくれるので助かります。
一度にたくさん作ってたくさん食べられる具だくさんの汁物は「一汁一菜」の強い味方です。
詳しい作り方はレシピのページに載せています。
とっても身体が温まりますので、よろしければ作ってみてください!
とても寒い日が出てきましたが、そんな時は温かい汁物を食べるとホッとします。
テレビで「秘密のケンミンショー」をたまに見るのですが、以前「石狩鍋」について特集していて、とても美味しそうでした。
そこで真似っこしてお味噌汁を作りました。

材料は、人参、キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、えのきだけ、鮭のアラ、味噌、酒粕、だし汁、です。
材料を食べやすい大きさに切り、だし汁でやわらかくなるまで煮込みます。
最後に味噌を溶き入れ酒粕を加えて出来上がりです。
とても簡単にアレンジして作りました。
本場のかたにはダメ出しされそうですが、「石狩鍋風」ということでお許しくださいね。
お味噌汁はレシピ通りきっちりと分量を守らなくても失敗しにくく、美味しく出来上がるので嬉しいです。
酒粕が無いときは味噌だけでも野菜の甘みが出て美味しくいただけます。
テレビ番組では、本場の石狩市では鍋と言うより大きなお椀によそってお味噌汁のように食べると言っていました。
そして、鮭は身ではなく必ずアラを入れるそうです。
身は焼いて食べるとか・・・。
番組ではおうちのお母さんが大きな鮭をまるまる一匹さばいていました!すごいです!
魚のお味噌汁は好きなのですがレパートリーが少なかったので、うれしい発見でした。
こちらのブログで以前書かせてもらいました「一汁一菜」を楽しんで実行しています。
子どもも好き嫌いは色々あるのですが、お味噌汁は必ず完食してくれるので助かります。
一度にたくさん作ってたくさん食べられる具だくさんの汁物は「一汁一菜」の強い味方です。
詳しい作り方はレシピのページに載せています。
とっても身体が温まりますので、よろしければ作ってみてください!
2017-12-04 08:00:00
現代栄養学と薬膳
カテゴリ : [月]管理栄養士の食事ノート
いつも「管理栄養士の食事ノート」を読んで下さり、どうもありがとうございます。
私は「公益社団法人 日本栄養士会」に所属しております。
すると毎月、「日本栄養士会雑誌」という機関紙が届けられます。
10月号から「薬膳の新たな展望」という連載が始まり楽しみに読んでいます。
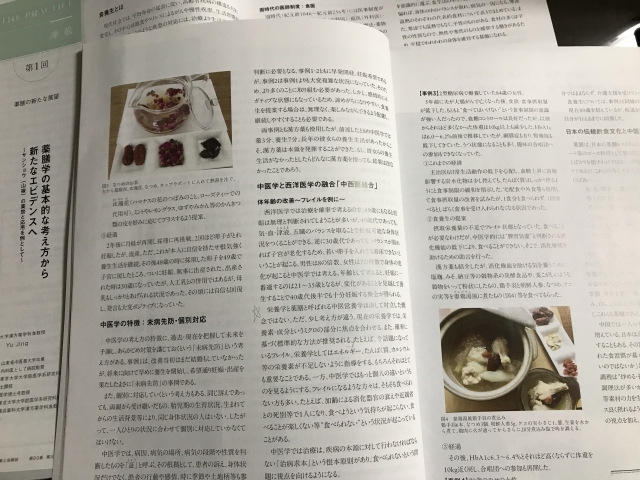
書かれているのは、大学の漢方薬学科の准教授や漢方専門薬局代表で中国出身の先生(医師)です。
今までは、栄養士の栄養指導と薬膳は考え方やアプローチが少し違うので、あまりこういった公式の栄養士専門誌に連載されているのを見かけたことがなく、少し驚きました。
第1回の10月号には中国医学の歴史や基礎知識をわかりやすく説明されていました。
(改めて、あまりの歴史の古さにビックリでした。。)
現代栄養学にはない、四気(感熱温涼)や五味の考え方もわかりやすく説明されていました。
第2回の11月号は49歳で妊娠・出産された事例を2例紹介されていました。
お二人とも一朝一夕ではありませんでしたが、漢方薬や治療に加え、根気強く前向きに食養生をされたそうです。
先生は。栄養学と薬膳は決して対立した概念ではなく、ただ少し考え方が違う、と言われています。
現在の栄養学では栄養素・成分というミクロの部分に焦点を合わせ、確立に基づく標準的な方法を推奨するが、
中医学ではもっと個人の違いというものを見るようにする、とあります。
また、先生は中国の医師たちに「日本の優れた食習慣が基本にあるからこそ、(日本での治療が)良い結果を残せるのではないか」と質問されたそうです。
中国の調理は炒める、揚げる等、素材の力を失わせてしまいやすいものが多いですが、
和食は煮る、焼く、蒸す等素材の力を生かした調理法が多く、
栄養素がバランスよく摂れるような献立スタイルになっています。
この食文化の上に薬膳の視点を加えていけばさらに充実した食養生を実践できるのではないか・・・と締めくくられていました。
古くて新しい食科学ですね!
和食も中国医学の食養生も、伝統的に受け継がれてきたものは、やはり本物なんだなぁと思いました。
これから、私たち栄養士が今まで欠けていた視点を補っていけば
もっと患者様・お客様の生活や人生の質を上げる食事を提案できる、
もっと個人に合ったオーダーメイドの栄養指導ができると思い、
そんな未来を想像してワクワクしました。
私は「公益社団法人 日本栄養士会」に所属しております。
すると毎月、「日本栄養士会雑誌」という機関紙が届けられます。
10月号から「薬膳の新たな展望」という連載が始まり楽しみに読んでいます。
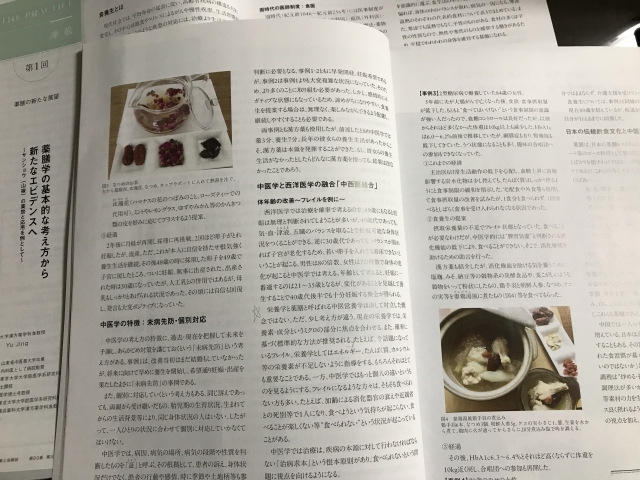
書かれているのは、大学の漢方薬学科の准教授や漢方専門薬局代表で中国出身の先生(医師)です。
今までは、栄養士の栄養指導と薬膳は考え方やアプローチが少し違うので、あまりこういった公式の栄養士専門誌に連載されているのを見かけたことがなく、少し驚きました。
第1回の10月号には中国医学の歴史や基礎知識をわかりやすく説明されていました。
(改めて、あまりの歴史の古さにビックリでした。。)
現代栄養学にはない、四気(感熱温涼)や五味の考え方もわかりやすく説明されていました。
第2回の11月号は49歳で妊娠・出産された事例を2例紹介されていました。
お二人とも一朝一夕ではありませんでしたが、漢方薬や治療に加え、根気強く前向きに食養生をされたそうです。
先生は。栄養学と薬膳は決して対立した概念ではなく、ただ少し考え方が違う、と言われています。
現在の栄養学では栄養素・成分というミクロの部分に焦点を合わせ、確立に基づく標準的な方法を推奨するが、
中医学ではもっと個人の違いというものを見るようにする、とあります。
また、先生は中国の医師たちに「日本の優れた食習慣が基本にあるからこそ、(日本での治療が)良い結果を残せるのではないか」と質問されたそうです。
中国の調理は炒める、揚げる等、素材の力を失わせてしまいやすいものが多いですが、
和食は煮る、焼く、蒸す等素材の力を生かした調理法が多く、
栄養素がバランスよく摂れるような献立スタイルになっています。
この食文化の上に薬膳の視点を加えていけばさらに充実した食養生を実践できるのではないか・・・と締めくくられていました。
古くて新しい食科学ですね!
和食も中国医学の食養生も、伝統的に受け継がれてきたものは、やはり本物なんだなぁと思いました。
これから、私たち栄養士が今まで欠けていた視点を補っていけば
もっと患者様・お客様の生活や人生の質を上げる食事を提案できる、
もっと個人に合ったオーダーメイドの栄養指導ができると思い、
そんな未来を想像してワクワクしました。
2017-11-20 08:00:00
赤ちゃんが何でも舐めたがるわけ
カテゴリ : [月]管理栄養士の食事ノート
いつも「管理栄養士の食事ノート」をお読みくださり、ありがとうございます。
先週はよく晴れた日が続きましたね。
お出かけがしたくなり、息子と二人で和歌山城の動物園と二の丸庭園に行って来ました。
気持ちの良い陽気で、楽しい一日を過ごすことが出来ました。
二の丸では、息子より小さい男の子が、ママとおばあちゃんと一緒に来ていました。
よちよちと息子に近づいて来てくれて、とてもかわいらしかったです。
その男の子が遊んでいる時に落ちている葉っぱか小石かを拾って舐めてしまい、おばあちゃんとママに「それは舐めんでいいから~」と注意半分で笑われていました。
うちの息子も以前よく庭の小石を舐めてしまったなぁ(笑)と思い出しました。
(その後は間違って飲み込んでしまわないように取り上げましたが。)
息子が生まれてから、こうしん堂の先生方に、何でも舐めることについて行き過ぎた清潔よりも多少色々舐めた方が良いよ、と聞いていたおかげで、そのへんは神経質になりすぎずにいました。
(もちろん、明らかに毒になるものや誤飲にはしっかりと注意しました。)
そして改めて最近、赤ちゃんが何でも舐めるわけについて、
有機農法や微生物を専門にお仕事をされている方が
藤田絋一郎さんの「脳はバカ、腸はかしこい」を引用して書かれている記事を目にしたところでした。
簡単に内容を紹介させてもらいます。
記事を省略して書かせてもらいますので少しわかりにくいかもしれませんが。。。
ちなみにこの方は常々、子どもがぜんそくなどにならないために「落ちたものを拾って食べましょう」と呼び掛けているそうです(笑)
・・・人間の子どもはお母さんの胎内にいる10か月と生まれてからの数か月で生物の進化をたどるような「個体発生と系統発生」を繰り返しています。
40億年前、放射能の影響が少ない深い海の底に生物が生まれました。
胎児も最初に羊水の中に発生します。(羊水と海とはほぼ同じ成分でてきています。)
また、生物が最初に誕生した地球には酸素がありませんでした。
生命が誕生する子宮の中にも酸素がなく同じような状況と言えます。
やがて地球に酸素が少しずつ増えてくると、生物は好気的な細菌を細胞の中に取り入れてミトコンドリアにし、酸素をエネルギー源とする種に変化しました。その時の動物には腸だけしかありませんでした。
お母さんの胎内でも臍帯から酸素をもらうようになった胎児は「動物のような成長」をします。
まず腸が最初に作られます。脳や心臓はそのあと。
10か月目に胎児は母親の胎内から出てきます。その時は10か月早産で生まれるので「一人前の人間」ではありません。
酸素が増えてきた地球上に住んでいた原始的な脊椎動物と同じ状態なのです。
彼らの多くは大地で泥まみれの生活をしていました。土を舐めていたのです。
人間の赤ちゃんが何でも舐めたがるのは理由があったのです。
それは土のうえにいた原始的な動物と同じ状態にあるからです。
なんでも舐めて赤ちゃんの腸を大腸菌だらけにしようとしているのです。
その証拠に決まって普通に生まれた直後の赤ちゃんの腸は大腸菌だらけになります。
赤ちゃんが何でも舐めたがるのを「ばっちぃ」といって阻止すると、その後赤ちゃんの腸は正常な発育を望めなくなるのです・・・
私の経験ですが、子どもが色々と舐めるのを親がどんなにがんばって阻止しても、絶対にこっそりと色んなものを舐めるので(笑)、ある意味安心です。
地球の誕生、生命の誕生、人と微生物の関係、、、長い長い歴史があり、赤ちゃんはそれを忠実に実行していると思うと本当に奥深いなと思いました。
子どもの食について、栄養のこと以外にも大切なことはたくさんあると、改めて広い視野を持つ必要を感じました。
先週はよく晴れた日が続きましたね。
お出かけがしたくなり、息子と二人で和歌山城の動物園と二の丸庭園に行って来ました。
気持ちの良い陽気で、楽しい一日を過ごすことが出来ました。
二の丸では、息子より小さい男の子が、ママとおばあちゃんと一緒に来ていました。
よちよちと息子に近づいて来てくれて、とてもかわいらしかったです。
その男の子が遊んでいる時に落ちている葉っぱか小石かを拾って舐めてしまい、おばあちゃんとママに「それは舐めんでいいから~」と注意半分で笑われていました。
うちの息子も以前よく庭の小石を舐めてしまったなぁ(笑)と思い出しました。
(その後は間違って飲み込んでしまわないように取り上げましたが。)
息子が生まれてから、こうしん堂の先生方に、何でも舐めることについて行き過ぎた清潔よりも多少色々舐めた方が良いよ、と聞いていたおかげで、そのへんは神経質になりすぎずにいました。
(もちろん、明らかに毒になるものや誤飲にはしっかりと注意しました。)
そして改めて最近、赤ちゃんが何でも舐めるわけについて、
有機農法や微生物を専門にお仕事をされている方が
藤田絋一郎さんの「脳はバカ、腸はかしこい」を引用して書かれている記事を目にしたところでした。
簡単に内容を紹介させてもらいます。
記事を省略して書かせてもらいますので少しわかりにくいかもしれませんが。。。
ちなみにこの方は常々、子どもがぜんそくなどにならないために「落ちたものを拾って食べましょう」と呼び掛けているそうです(笑)
・・・人間の子どもはお母さんの胎内にいる10か月と生まれてからの数か月で生物の進化をたどるような「個体発生と系統発生」を繰り返しています。
40億年前、放射能の影響が少ない深い海の底に生物が生まれました。
胎児も最初に羊水の中に発生します。(羊水と海とはほぼ同じ成分でてきています。)
また、生物が最初に誕生した地球には酸素がありませんでした。
生命が誕生する子宮の中にも酸素がなく同じような状況と言えます。
やがて地球に酸素が少しずつ増えてくると、生物は好気的な細菌を細胞の中に取り入れてミトコンドリアにし、酸素をエネルギー源とする種に変化しました。その時の動物には腸だけしかありませんでした。
お母さんの胎内でも臍帯から酸素をもらうようになった胎児は「動物のような成長」をします。
まず腸が最初に作られます。脳や心臓はそのあと。
10か月目に胎児は母親の胎内から出てきます。その時は10か月早産で生まれるので「一人前の人間」ではありません。
酸素が増えてきた地球上に住んでいた原始的な脊椎動物と同じ状態なのです。
彼らの多くは大地で泥まみれの生活をしていました。土を舐めていたのです。
人間の赤ちゃんが何でも舐めたがるのは理由があったのです。
それは土のうえにいた原始的な動物と同じ状態にあるからです。
なんでも舐めて赤ちゃんの腸を大腸菌だらけにしようとしているのです。
その証拠に決まって普通に生まれた直後の赤ちゃんの腸は大腸菌だらけになります。
赤ちゃんが何でも舐めたがるのを「ばっちぃ」といって阻止すると、その後赤ちゃんの腸は正常な発育を望めなくなるのです・・・
私の経験ですが、子どもが色々と舐めるのを親がどんなにがんばって阻止しても、絶対にこっそりと色んなものを舐めるので(笑)、ある意味安心です。
地球の誕生、生命の誕生、人と微生物の関係、、、長い長い歴史があり、赤ちゃんはそれを忠実に実行していると思うと本当に奥深いなと思いました。
子どもの食について、栄養のこと以外にも大切なことはたくさんあると、改めて広い視野を持つ必要を感じました。
2017-11-06 08:00:00
七十二候のはなし
カテゴリ : [月]管理栄養士の食事ノート
いつも「管理栄養士の食事ノート」をお読みくださり、どうもありがとうございます。
我が家で利用している食材の宅配業者さんのチラシで、定期的に書かれている記事「七十二候(しちじゅうにこう)」のお話しを読んでいます。
「二十四節気(にじゅうしせっき」はよく目にしていましたが、こちらの「七十二候」はあまりなじみがありませんでした。
七十二候・・・
二十四節気をさらに約5日ずつ、順に初候、次候、末候と分けたもの。
それぞれに、気象の変動や生き物の動向を写した、季節の移ろいを表す名がつけられている。
日本に伝来してから、日本の気候風土に合わせて改訂されている。
10月23日から27日は「霜降(そうこう)」の「霜始降(しもはじめてふる)」だそうです。
昔はこのころになると冷え込みが増し、霜が降りるようになったのでしょうか?
10月28日から11月1日は「霜降」の「こさめ時降(こさめときどきふる)」です。
こさめは時雨ともいい、晩秋から初冬の間に降る、通り雨のことだそうです。
そして、昔は旧暦の9月13日にも「十三夜のお月見(後の名月)」をして、栗や枝豆を備えたそうです。
今年は11月1日にあたるそうです。
二十四節気や七十二候を意識して暮らすと、自然は刻一刻と変化していくことを思い出し、同じような毎日をバタバタと忙しく暮らしていますが、一日ごと全てが同じ日ではない特別な時間であることに気付かされます。
そして、季節の自然の恵みの食べ物がより美味しくありがたくご馳走に感じます。
さて、23日更新のブログですが、たった今、書いているのは22日(日)です。
台風が近づいてきています。
我が家の窓に激しく雨が降りつけて、けたたましく携帯の避難勧告のアラームがなっています。
どの地域にお住いのかたも、皆様が無事でありますように願います。
自然は時に本当に怖いです。
そして、日々自然の移ろいを意識していくことは、自然の事象に対して畏敬の念を持つことにつながっていくように思いました。
我が家で利用している食材の宅配業者さんのチラシで、定期的に書かれている記事「七十二候(しちじゅうにこう)」のお話しを読んでいます。
「二十四節気(にじゅうしせっき」はよく目にしていましたが、こちらの「七十二候」はあまりなじみがありませんでした。
七十二候・・・
二十四節気をさらに約5日ずつ、順に初候、次候、末候と分けたもの。
それぞれに、気象の変動や生き物の動向を写した、季節の移ろいを表す名がつけられている。
日本に伝来してから、日本の気候風土に合わせて改訂されている。
10月23日から27日は「霜降(そうこう)」の「霜始降(しもはじめてふる)」だそうです。
昔はこのころになると冷え込みが増し、霜が降りるようになったのでしょうか?
10月28日から11月1日は「霜降」の「こさめ時降(こさめときどきふる)」です。
こさめは時雨ともいい、晩秋から初冬の間に降る、通り雨のことだそうです。
そして、昔は旧暦の9月13日にも「十三夜のお月見(後の名月)」をして、栗や枝豆を備えたそうです。
今年は11月1日にあたるそうです。
二十四節気や七十二候を意識して暮らすと、自然は刻一刻と変化していくことを思い出し、同じような毎日をバタバタと忙しく暮らしていますが、一日ごと全てが同じ日ではない特別な時間であることに気付かされます。
そして、季節の自然の恵みの食べ物がより美味しくありがたくご馳走に感じます。
さて、23日更新のブログですが、たった今、書いているのは22日(日)です。
台風が近づいてきています。
我が家の窓に激しく雨が降りつけて、けたたましく携帯の避難勧告のアラームがなっています。
どの地域にお住いのかたも、皆様が無事でありますように願います。
自然は時に本当に怖いです。
そして、日々自然の移ろいを意識していくことは、自然の事象に対して畏敬の念を持つことにつながっていくように思いました。
2017-10-23 08:00:00






